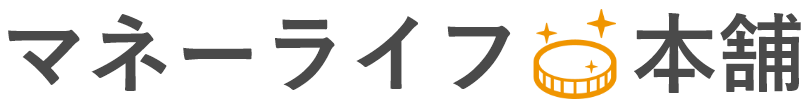若い世代の人が一戸建てやマンションなどの住宅を購入しようと考える時に、住宅ローンを組む際に頭金が足りないので親に支援を受けるという事例はよくあるものです。しかし親だからといって簡単に子どもにお金を贈与できるわけではありません。その際の注意点をここでは挙げていきます。
 変動金利/(頭金10%以上)指定の口座開設で頭金なしでも0.590% | 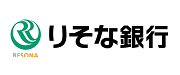 りそな住宅ローン 変動金利 |  金利プラン(新規お借入れ)※物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | |
|---|---|---|---|
| 金利タイプ | 変動金利 | 変動金利 | 変動金利 |
| 金利 | 年0.590% | 年0.640% | 年0.830% |
| おすすめ | ・諸費用込みのフルローンを希望 ・無料の特約付き団信を希望 ・勤続年数短い人 | ・頭金なしのフルローン(諸費用込み融資OK) ・注文住宅を予定(土地先行融資、分割融資OK) | ・物件価格の80%超(頭金20%未満。頭金なしもOK)で借入れする通常金利のプランです。頭金20%以上入れると年0.780%まで優遇されます ・日常の買い物はイオングループでする人 |
| 保証料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 事務手数料 (税込) | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20% +55,000円 | 借入金額×2.20% |
| 一般団信 保険料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 無料の 特約付き団信 | 介護保障 (65歳以下) | – | 全疾病保障 (49歳まで) |
| 借入可能額 | 500万円~3億円以下 | 50万円~3億円 | 200万円以上2億円以内 |
| 対応地域/来店 | 全国/不要 | 全国/不要 | 全国/不要 |
| 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
\総支払額の試算も可能/
住宅ローンの費用を親から援助してもらう場合
親から贈与で援助してもらう
まず住宅ローンを組もうと思っても、その人の年収によりローンを組める最大の金額は変動します。
35年ローンを考えた時に、銀行や会社によって異なりますが、一般的には年収の6~7倍が上限というところが多いでしょう。そのため頭金を多く用意して住宅購入資金にしたいところでしょうが、特に若い世代ほど貯金がないので頭金に充てられる金額も少ないケースが多いです。そういった時に親世代から1,000万円や2,000万円などのまとまったお金の支援を受ける人もいます。
しかし親と子の関係でもお金を贈与するときには贈与税がかかってきます。年間110万円までは無税ですがそれを超えると税金がかかり、例えば1,000万円贈与した場合は231万円の贈与税を、受け取った子どもが支払わなくてはいけません。
親から貸与で援助してもらう
せっかく子どものことを思って住宅資金を贈与をしたのに、税金で多く持って行かれては意味が無いと思う人も多いでしょう。では税金で持っていかれないためにどうしたら良いのかというと、まず一つの手段としては住宅ローンを組む際の頭金を、あくまでも親から子への貸与ということにするのです。
貸与ならば税金はかかりませんが、その代わりにきっちりと貸与という事実を証明するために借用書または金銭消費貸借契約書を作成する必要があります。また借用書の内容も1,000万円を借りたのに、利息が0だったり1年1万円だけ返済して1,000年で返すなどの非現実的なものは認められません。
また返済も証拠が残るように親の銀行口座に振り込んだり、領収書を作成しておく必要があります。年間110万円までは無税で贈与できるので、このシステムと併用すれば節税が可能です。
借用書は借りた人が作成し、貸し手に渡す1通のみですが、
金銭消費貸借契約書の場合、両者が押印した契約書を相互に保管しておきます。
証拠としての能力としては同等です。
親と共同で住宅購入する
もう一つ子どもへ住宅ローンの頭金を援助したい時に利用できるのが親と子の共同購入にするという方法です。
共同名義で購入して実際には子ども世帯がメインに住み、親が亡くなった後に相続をするというケースです。
かなり大規模の住宅になってしまわないかぎりは相続税も発生しないことが多いので、将来的には無税で子ども世帯に家が残せます。ただし注意をしなければいけないのは兄弟が多い場合です。
例えば父が亡くなった際に残った資産は配偶者に半分、残りを兄弟で分けます。
次男の住宅を父との共同名義で購入していた場合、長男にもその次男の住宅の一部を相続する権利が発生します。
遺言で言い残しておく、家族内で話し合えるならばトラブルは起きにくいでしょうが、その以前から家族間にトラブルが発生していた際には、揉め事が起きる可能性もあるので注意しておきましょう。
親や親族からの資金援助の注意点

資金源についての確認
親や親族から資金援助を受ける時には、その資金源についても確認しておく必要があります。
その資金が違法な手段で手に入れたものである場合、問題が発覚した時に、購入した住宅も合わせてトラブルに巻き込まれることがあるからです。
また、資金援助を受ける人の返済能力も大事なポイントになります。いくら返済している証拠があっても、実際に収入が不安定であれば、本当に返済をしているのか税務署から疑われても仕方がないでしょう。
さらに親や親族の年齢にも注意が必要です。資金援助をする人が90歳近くになっているなら、最後まで返済する意思が無い、事実上の贈与に当たると判断されることもあるのです。
このように、親や親族から資金援助を受ける際には、外部から見ても不自然でない方法が必要となるのです。
相続時精算課税制度の特例
住宅を取得するための資金援助には、特例も設けられています。住宅取得等資金贈与にかかる相続時精算課税制度の特例を選択して活用です。 これは、住宅を購入する資金準備にあたり贈与を受ける際には、贈与税と相続税を合わせた課税方式で生前贈与が行ないやすくなる制度です。
贈与の金額には非課税枠が設けられており、その範囲であれば非課税になります。贈与の金額が非課税の枠を超えた場合には、一律で20%の税率が課されることになりますが、相続税額から控除される仕組みになっています。
親からの援助は方法も多様だが、注意すべき点も
住宅ローン費用を親から援助を受ける場合の方法についてご紹介してきました。
- 年間110万以上贈与を受ける場合は、贈与税がかかる
- 貸与する場合は借用書または金銭消費貸借契約書が必要
- 共同購入は無税になるが、兄弟がいる場合は注意
- 援助を受ける場合、出所や課税枠も確認を
援助を受ける方法は様々です。その分税金がかかる場合やトラブルのものになるリスクもあります。
ご自身の状況に合わせた援助の受け方を模索してみましょう。

マネーライフ本舗 編集部
住宅ローンをはじめとした住宅購入に役立つ情報をお届けしています。また住宅ローンの一括仮審査申し込み・火災保険の見積もりサービスもございますので、ぜひご利用ください!