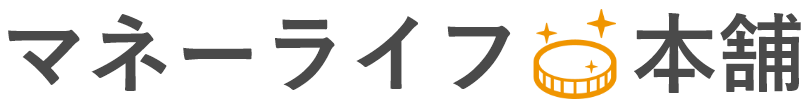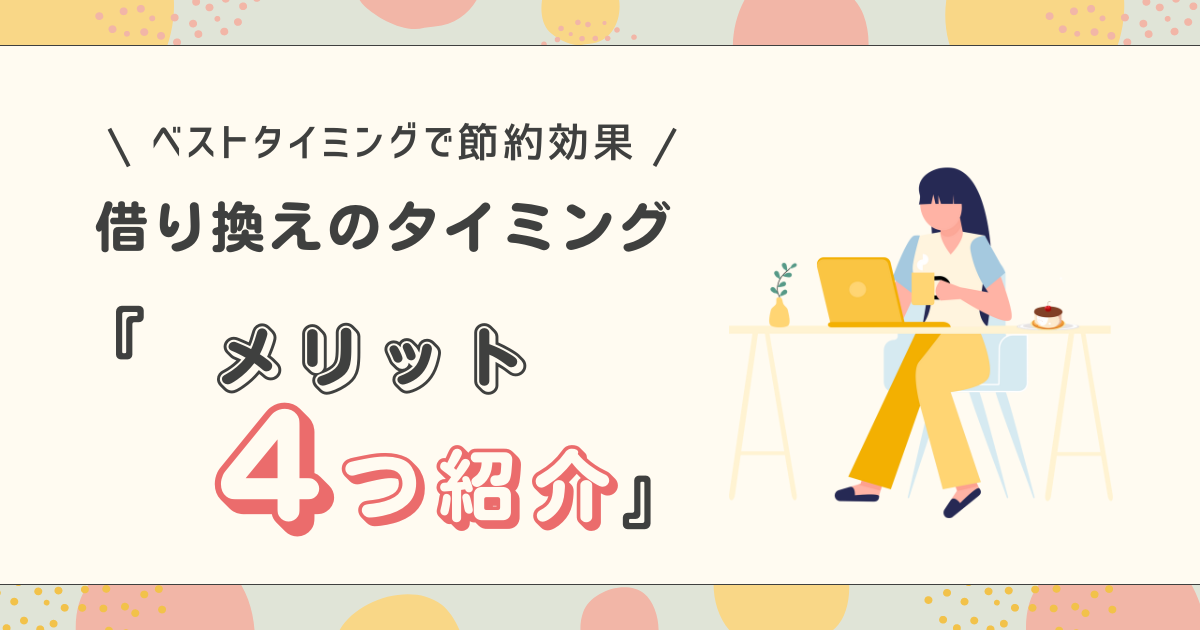住宅ローンを返済していく上で、より条件の良い住宅ローンに借り換えることは大切です。ところで、自分の場合は借り換えをしたほうがいいのか?審査のための条件は?どのくらいメリットがあるのか?という疑問をお持ちではないでしょうか。
そこで、今回は住宅ローンの借り換えのタイミングと、実際にメリットがあるケース、借り換え時の注意点をご紹介します。
 金利優遇キャンペーン9/30まで(変動金利) | 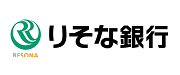 りそな住宅ローン 変動金利 |  金利プラン(新規お借入れ)※物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | |
|---|---|---|---|
| 金利タイプ | 変動金利 | 変動金利 | 変動金利 |
| 金利 | 年0.590% | 年0.640% | 年0.830% |
| おすすめ | ・諸費用込みのフルローンを希望 ・無料の特約付き団信を希望 ・勤続年数短い人 | ・頭金なしのフルローン(諸費用込み融資OK) ・注文住宅を予定(土地先行融資、分割融資OK) | ・物件価格の80%超(頭金20%未満。頭金なしもOK)で借入れする通常金利のプランです。頭金20%以上入れると年0.780%まで優遇されます ・日常の買い物はイオングループでする人 |
| 保証料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 事務手数料 (税込) | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20% +55,000円 | 借入金額×2.20% |
| 一般団信 保険料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 無料の 特約付き団信 | 介護保障 (65歳以下) | – | 全疾病保障 (49歳まで) |
| 借入可能額 | 500万円~3億円以下 | 50万円~3億円 | 200万円以上2億円以内 |
| 対応地域/来店 | 全国/不要 | 全国/不要 | 全国/不要 |
| 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
\総支払額の試算も可能/
住宅ローンの借り換えとは?
住宅ローンの借り換えとは、今借りている金融機関から、新たな他の金融機関で住宅ローンの契約をし直して現在借りている住宅ローンの残金を一括返済することです。2024年ゼロ金利時代は終わりましたが、それでも、日本では低金利が続いているため、昔契約した住宅ローンより金利が低くなっていることが多くあります。
金利の高い住宅ローンから金利の低い住宅ローンに借り換えをすると、総支払額や月々の返済額が減る可能性が高いです。
自分が借り換えをした場合、どのくらいの支払額になるのかまずは見てみたいという方は、住宅ローン借り換えシミュレーションからチェックしてみるのがおススメです。
住宅ローン借り換えのタイミング
住宅ローンの借り換えは金融機関の定めている基準を満たしていれば、いつでもすることが可能となり、一律の基準はありません。しかし、タイミングによっては、あまり支払金額が減らなかったり、準備や審査などの手間がかかるだけでメリットが少ない場合もあります。
なるべく多くのメリットを受けるためには、ベストなタイミングで借り換えをすることが大切です。
借りたときよりも金利が低くなっているとき
借り換えのタイミングとしてまず一番に挙げられるのが、当初住宅ローンを借りたときよりも金利が下がっている場合です。一般的に、金利差が大きいほど借り換えの効果も高くなります。1%以上の金利差がある場合にメリットが多くなるといわれることが多いですが、金利差0.3%以上であれば、諸費用などのシミュレーションをした上で借り換えを検討してみてもよいかもしれません。
変動金利の決まり方
変動金利は「短期プライムレート」を基準として設定されています。
短期プライムレートとは、金融機関が大手企業等、優良企業向けに1年未満の期間の貸出に適用する最優遇金利のことを指します。金利は半年に一度見直しが行われ、短期プライムレートの金利が上昇すると、変動金利も上昇します。これまで続いてきたゼロ金利時代も終わり、令和6(2024)年 9月 2日 1.625%に上がっています。
参考:長・短期プライムレート(主要行)の推移 2001年以降
固定金利の決まり方
固定金利は、国債市場で取引される10年物国債の利回りを基準として金利が設定されています。物価や為替、景気などを主な要因とし、景気が良くなると金利は上昇し、景気が悪くなると金利は低下するということになります。投資家の将来予測も大きな影響を及ぼします。
収入が下がる前や、転職を予定しているとき
借り換えをする際は再度審査が必要となり、勤続年数は審査をする上で重要な項目です。勤続年数が短い場合でも審査の申し込み自体は可能ですが、審査に通りづらくなる可能性もあります。
国土交通省の調査、「民間金融機関が住宅ローンを融資する際に考慮している項目」を見ると、5番目に勤続年数を判断基準としていることが分かります。
| 完済時年齢 | 98.7% |
|---|---|
| 健康状態 | 97.9% |
| 借入時年齢 | 97.2% |
| 担保評価 | 96.1% |
| 勤続年数 | 93.2% |
ローン残高1,000万円以上、残りの返済期間10年以上のとき
借り換えをしてメリットがあるのは、ローンの返済期間が残り10年以上、ローンの残高が1,000万円以上、借り換え後との金利差が1%以上ある場合と言われています。尚、昔に比べ借り換え時の諸費用が、ネット銀行などにより安くなっているため、金利差が1%以下の場合でも総支払額が減る可能性もあります。
固定金利特約期間が終わったとき
固定金利特約型とは(3・5・10・20年)等、選択した年数の一定期間、金利が固定されます。
その期間が終了すると再度金利タイプを選びなおす必要があるため、特約期間が終わるタイミングは借り換えのタイミングと言えます。特約期間終了時の金利と比較し、金利が低くなる金融機関を検討しましょう。
月々の返済が厳しくなりそうなとき
住宅ローンは一度借りてしまうと、中々見直しをしようと思うきっかけが多くありません。
しかし、子供が生まれて月々の支出が増えそうなときや、一緒に住んでいるパートナーが仕事を辞め収入が減りそうなとき等、月々の収支が変わりそうな時は借り換えを検討するタイミングです。
昨今は、低金利が続いているため、数年前に借りたときと比較し大きく金利が下がっている可能性があり、その場合は総支払額の減少が見込めます。住宅ローンを借りてから1年以上経過している方は、過去の金利推移をチェックしてみるのがおススメです。
住宅ローンの借り換えのメリット
住宅ローンの借り換えをするとどのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットは以下の4つになります。
・ローンの総返済額を減らすことが出来る
・返済期間を調整することが出来る
・金利タイプの変更が出来る
・団体信用生命保険の保障内容を見直すことが出来る
ローンの総返済額を減らすことが出来る
借り入れ中の住宅ローンよりも低い金利の商品に借り換えをすれば利息を下げることができ、同じ返済期間でも返済額が減少します。毎月の返済額や返済総額を減らせるので、家計負担の軽減につながります。
2016年1月に日本ではマイナス金利政策が導入されているため、2016年以前に住宅ローンを組んでいる方はほとんどの方が借り換えで大きなメリットを受けられるでしょう。
住宅ローンの借り換え前後の金利差が1.0%以上あった場合
一般的に借り換え前後の金利差が大きいほど借り換えの効果も大きいといわれています。
仮に1.0%の金利差でどのくらいの効果があるのか、シミュレーションをしてみました。
<条件>
フラット35(全期間固定)
ローン残高:2,500万円
ローン残年数:25年
金利:2.5%→1.5%
単位:円
| 毎月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 | うち利息分 | 諸費用 | 総支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借り換え前(A) | 112,154 | 1,345,848 | 33,646,064 | 8,646,064 | 1,257,200 | 34,903,264 |
| 借り換え後(B) | 99,984 | 1,199,806 | 29,995,049 | 4,995,049 | 1,409,200 | 31,404,249 |
| 差額(B-A) | -12,170 | -146,040 | -3,651,015 | -3,651,015 | –152,000 | -3,499,015 |
シミュレーションの結果では、借り換え後では、諸費用を差し引いても約350万円も軽減できることになります。ローンの残高やローン残存年数が大きく、借り換え後の金利が低ければ、さらに軽減できる可能性があります。
※借り換え後の諸費用には、団信保険料と印紙税2万円、登録免許税10万円、司法書士報酬7.5万円を含んでいます。
返済期間を調整することが出来る
借り換えをする際には、返済期間の調整が可能です。
金利タイプの変更が出来る
借り換えをする際には、金利タイプの変更が可能です。
- ・変動金利→固定金利に変更する場合
-
返済期間中の金利が一定となる全期間固定金利タイプのローンに借り換えをすると、今後金利上昇のリスクはありません。基本的に変動金利よりは金利が高くなりますが、昨今は低金利が続いているため、安定した一定の金額で返済していきたいという方にはおススメと言えます。
- ・固定金利→変動金利に変更する場合
-
変動金利は固定金利より金利が低く設定されていますが、変動金利は半年に1回金利の見直しがあるため、金利が上昇すると返済負担は大きくなります。現在の負担を減らしたいという方にはおススメですが、将来の金利上昇リスクは予想できません。金利が上昇し、月々の返済額が増えた場合にも返済出来るよう貯金などのリスク対策が出来ていれば、現在の低金利では大きな返済額減少が見込めるでしょう。
団体信用生命保険の保障内容を見直すことが出来る
同じ住宅ローン内で今加入している団信から新しい団信に保障内容を変更することは出来ません。借り換えのタイミングで保障内容を見直すチャンスとなります。
団信の保障内容は金融機関により異なります。
例えば、auじぶん銀行やソニー銀行では、金利上乗せなしで、がんと診断確定時に住宅ローン残高の50%が保障されます。住信SBIネット銀行では、全疾病保障が自動で付帯され、50歳未満の方には、併せて三大疾病50%補償が付帯されます。
団体信用生命保険の比較やおすすめについては以下の記事で詳しく解説しています。
住宅ローンの借り換えのデメリットと注意点
住宅ローンの借り換えをする際は、メリットだけではなく下記3つのデメリットもあります。
・借り換えの手数料がかかる
・再審査をするための申込書類を揃える手間がかかる
・審査が厳しくなる可能性がある
借り換えの手数料がかかる
住宅ローンを借り換える際には、必ず手数料がかかるため、手数料を含めて総支払額が少なくなるかをシミュレーションして判断することがとても重要です。一般的に借り換えにかかる手数料は30万円~100万円ほどと言われてています。必要な手数料は金融機関や、借入金額により異なりますが、主に必要と言われる手数料をは下記となります。
| 費用対象 | 相場 |
|---|---|
| 全額繰り上げ返済手数料 | 0~5万円 |
| 保証料 | 0~5万円 |
| 融資事務手数料 | 定額型:3万円~10万円 定率型:借り換え金額の2.2%程 |
| 印紙税 | 0円~6万円 |
| 司法書士手数料 | 3万円~10万円 |
| 抵当権抹消費用/登録費用 | 土地建物各1,000円/借入金額×0.4% |
| 団体信用生命保険料 | 金利に含まれる場合もあり |
| 火災保険、地震保険料 | プランにより異なる |
全額繰り上げ返済手数料(借り換え前の金融機関)
現在借り入れしている住宅ローンを繰上返済(残高の全部を返済すること)する際に金融機関に支払う手数料です。借り入れしている金融機関によって金額は異なりますが、相場は0万円~5万円となっています。全額繰り上げ返済手数料がなしの金融機関もあります。
保証料(新しく借り入れする金融機関)
返済が滞ってしまった時等、保証会社から保証を受けるための費用です。保証会社が支払いを立て替えた場合は、住宅ローンの返済先が金融機関から保証会社に変わります。支払い方法は、住宅ローンの金利に上乗せして支払う「金利上乗せ方式」と、借り入れ時に一括で支払う「一括前払い方式」があります。
金利上乗せ方式
└借入金利に対して、年率0.2%程上乗せ
一括前払い方式
└借り換え金額の0%~2%程
融資事務手数料(新しく借り入れする金融機関)
住宅ローンの手続きに関する事務費用手数料です。融資事務手数料や事務取扱手数料等、金融機関により呼び方が異なります。「定額型」と「定率型」の2種類あります。
定額型
└3万円~10万円程
定率型
└借入金額×2.2%程
一般的には、返済期間が短い場合は事務手数料が定額型の方が総支払額が安くなり、返済期間が長い場合は事務取扱手数料が定率型の方が総支払額が安くなると言われています。同じ金融機関内で定率型と定額型の両方の住宅ローンがある場合は、総支払額シミュレーションでどちらのプランがトータルで安くなるのかをチェックしてみましょう。
印紙税
住宅ローンの契約書類にかかる税金です。金額は借入金額により異なります。
| 借入金額 | 金額 |
|---|---|
| 100万円~500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円~1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円~5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円~1億円以下 | 60,000円 |
司法書士手数料
抵当権の設定を司法書士に手続きを依頼する場合にかかる費用です。3万円~10万円が相場となります。
抵当権抹消費用、設定費用
全額繰り上げ返済を行うと、元々借り入れしていた金融機関の抵当権(金融機関が住宅ローンの返済を保証するための権利)は消滅します。この時に必要な手続きが「抵当権抹消登記」、新たな金融機関で抵当権を設定することを「抵当権設定登記」といいます。「抵当権抹消登記」では不動産1件につき1,000円、「抵当権設定登記」では借入金額×0.4%がかかります。
このように借り換えには、金融機関に払う手数料や登記に関する手数料等、様々な手数料がかかります。全ての手数料を合わせたうえで総支払額が減るかどうかを判断する必要があります。
再審査をするための申込書類を揃える手間がかかる
借り換えは、新しく住宅ローンを契約するということになるため、借り換え先の金融機関で改めて審査を受けることになります。新規で住宅ローンを借りたときと同様に必要書類を集めてから審査を受ける必要があります。必要書類は金融機関によって異なりますが、主に必要とされる書類は以下となります。
本人確認書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 運転免許証 | 自身で持っているもの |
| パスポート | 自身で持っているもの |
| 健康保険証 | 自身で持っているもの |
| 住民票の写し(発行後3か月以内の原本) | 市区町村窓口 |
収入証明書類
【給与所得者】
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 直近の源泉徴収票(原本) | 勤務先 |
| 直近の課税証明書(原本) | 市区町村窓口 |
| 住民税決定通知書(原本) | 勤務先(毎年6月ごろ) |
【個人事業主】
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書の控え(直近2~3年分) | 自身で持っているもの |
| 所得税納税証明書(発行後3か月以内の原本) | 税務署 |
物件関連書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 不動産登記事項証明書(発行後3か月以内の原本) | 法務局 |
| 売買契約書(コピー) | 不動産会社 |
| 重要事項説明書(コピー) | 不動産会社 |
借り換え関連書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 住宅ローン返済予定表(原本) | 現在借り入れ中の金融機関 |
| 返済用口座通帳(コピー) | 自身で持っているもの |
| 健康診断書(借入金額が5,000万円を超える場合) | 健康診断を受けた医療機関 |
このように、借り換えには多くの書類が必要です。間に合わないということがないよう、余裕をもって書類の準備をしておきましょう。
審査が厳しくなる可能性がある
審査が厳しくなる一番の理由は、当初住宅ローンを組んだ時よりも時間が経っていて、住宅の担保評価(価値)が下がっているためです。
それ以外で審査が厳しくなる可能性としては、「当初契約した時より住宅ローン以外の借り入れが増えている場合」や「健康状態が悪くなっている場合」などが挙げられます。
審査が厳しくなると言われる中で、フラット35は比較的審査が通りやすいとされています。中々審査に通らないという方は、フラット35を借り換えの候補に入れてもよいでしょう。
住宅ローン控除が受けられなくなる可能性がある
住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があり、借り換えの際に条件から外れてしまうと住宅ローン控除(減税)を受けることが出来なくなってしまいます。
- 返済期間が10年以上あること
- 控除を受ける年末(12/31)に住んでいること
- 床面積が50m2以上あること
- 床面積の50%以上が居住用であること
- 2以上の住宅を保有している場合は主として居住用であること
- 新築、中古住宅の場合は引渡しから6ヶ月以内に居住すること
- 合計所得金額が、2,000万円以下であること
特に、返済期間が10年以上であることという点には注意が必要です。
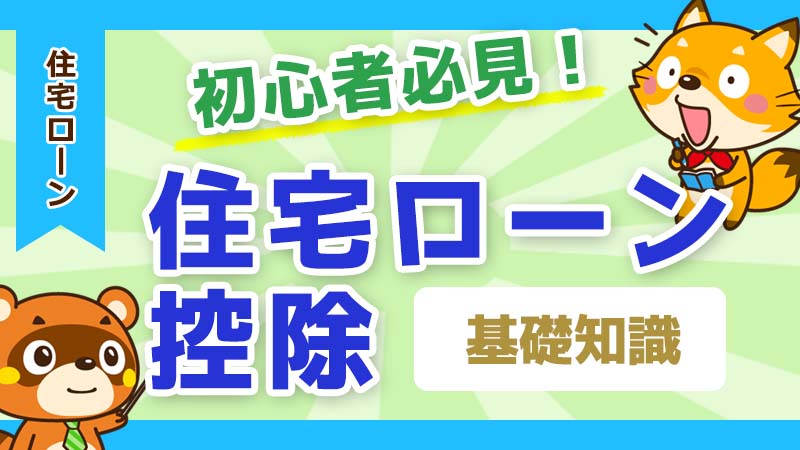
住宅ローン残高が少なくて、残存年数が短くても借り換えメリットはある?
借り換えでは、ローン残高が大きければ大きいほど、残存年数が長ければ長いほどメリットは大きくなるということが分かりました。
住宅金融支援機構の『2015年度 民間住宅ローン借換えの実態調査』を見てみると、実際に借り換えを行った人の半数以上が、借り入れから10年以内に実行しているのです。
したがって、借り入れから年数が経過するほど、借り換えを実行する割合が減っています。これは、住宅ローンの残存年数が少なくなると借り換えのメリットがなくなるというイメージを持っていらっしゃる方が多いのかもしれません。
それでは、住宅ローンの残高が少なくなり残存年数が10年未満では借り換えのメリットはないのでしょうか?
そこで、住宅ローン残高1,000万円以上かつ残存年数10年以上の場合と住宅ローンの残高が1,000万円未満かつ残存年数10年未満の場合についてシミュレーションをしてみましょう。
【ケース1】住宅ローン残高1,000万円以上かつ残年数期間10年以上の場合
<設定条件>
残高:1,500万円
返済期間:15年
固定金利:2.5%
毎月返済額:100,018円
総支払額:18,003,214円
単位:円
| 借り換え金利 | 諸費用 | 毎月返済額 | 総支払額 | 利息の軽減効果 | 利息の軽減額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00% | 無 | 96,526 | 17,529,634 | 効果あり | 473,580 |
| 2.00% | 有 | 97,913 | 18,103,426 | なし | – |
| 1.50% | 無 | 93,111 | 16,914,968 | 効果あり | 1,088,246 |
| 1.50% | 有 | 94,468 | 17,483,154 | 効果あり | 520,060 |
結果は、1.5%へ借り換えをした場合では、軽減効果は諸経費を考慮しなければ約100万円が、考慮しても約50万円になります。
【ケース2】住宅ローン残高1,000万円未満かつ残存年数10年未満の場合
<設定条件>
残高:750万円
返済残期間:7年
固定金利:2.5%
毎月返済額:97,418円
総支払額:8,183,127円
単位:円
| 借り換え金利 | 諸費用 | 毎月返済額 | 総支払額 | 利息の軽減効果 | 利息の軽減額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50% | 無 | 94,110 | 8,020.283 | 効果あり | 162,844 |
| 1.50% | 有 | 94,766 | 8,237,366 | なし | – |
| 0.50% | 無 | 90,875 | 7,748,538 | 効果あり | 434,589 |
| 0.50% | 有 | 91,517 | 7,964,399 | 効果あり | 218,728 |
結果は、「住宅ローン残高1,000万円未満かつ残存年数10年未満の場合」であっても少なからず効果が出ているのが分かります。現状より2%低い金利への借り換えであれば諸費用がかかっても約20万円の効果がありました。
※諸費用(有)のケースでは保証料0.2%を金利に上乗せしています。
シミュレーションでも触れましたが、借り換えでは借り入れをするための諸費用がかかります。各金融機関によって金額が異なりますが、諸費用を含めた上で、現状よりどのくらい総返済額が軽減できるのかを比較することがポイントになります。
「住宅ローン残高1,000万円以上、返済期間10年以上、金利差1%」というのはあくまでも目安です。
金利差1%未満でもメリットがでる可能性があるということです。
住宅ローンの借り換えはタイミングが大切!
住宅ローンについて借り換えを検討していたという方、またはすでに諦めていたという方も、これまでの金利推移をみても低金利の今こそチャンスと捉え、いくつかの金融機関でシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。